おはようございます。
酒田市の歯医者、沢田歯科医院の沢田です。
今回は「歯が溶けている時間」についてお話します。
食事のコントロールについてです。
この「歯が溶けている時間」について必要な「ステファンカーブ」についてお話します。
クリックすると新しいウィンドウで開きます
クリックすると新しいウィンドウで開きます
これがステファンカーブと呼ばれるグラフです。
朝・昼・夜に規則正しく食事をとった場合の、口腔内(歯についているプラーク)のph( 酸性、アルカリ性の程度を示す値)の移り変わりを表すと、上のようなグラフになります。
最初は弱アルカリ性(正常値)だった口腔内が、朝食事をとると急激に酸性になり、お昼になるにしたがってまた弱アルカリへと戻す。そしてまた昼食をとると酸性になり、また時間とともに弱アルカリに戻るといった具合になっていると思います。
つまり食事をとると口腔内は急激に酸性になります。だいたいpH5.4以下になると歯が溶け始めると言われていますので、食事をとった後しばらくの間、口腔内は酸で歯が溶けている状態ということになります。
しかし唾液にはこの酸性環境を弱アルカリ性(正常な状態)に戻す働きがあり、溶けはじめた歯の表面を再石灰化する力も持ち合わせています。
グラフを見ると唾液の力により時間とともに酸性になった口腔内がアルカリ性へと戻っていくのがわかりますね。
ちなみにこの唾液の作用は緩衝能(かんしょうのう)と呼ばれています。
緩衝能の力にも個人差があり、また唾液の量が多い人ほど虫歯にもなりにくいと言われています。
しかし、朝・昼・夜の決まった食事以外に間食をしてしまうなど、規則正しい食生活ではない人のステファンカーブは、下のグラフがそれを表しています。
このように、間食をたくさんすることで、歯を溶かしている時間を長く作っていることになり、
歯は再石灰化をする間もなく溶けている→虫歯になる
といったことになります。
虫歯予防に、食事のコントロールも大切なことがおわかりいただけたでしょうか?
このように虫歯になりやすいかどうかは、色々な原因が関係しています。
一度削ってしまった歯は戻りません。
予防がとても大切です。
定期的に検診を受け、予防を大切にしていただくことが、将来歯を長く持たせる方法です。
ぜひ定期的にご来院ください。




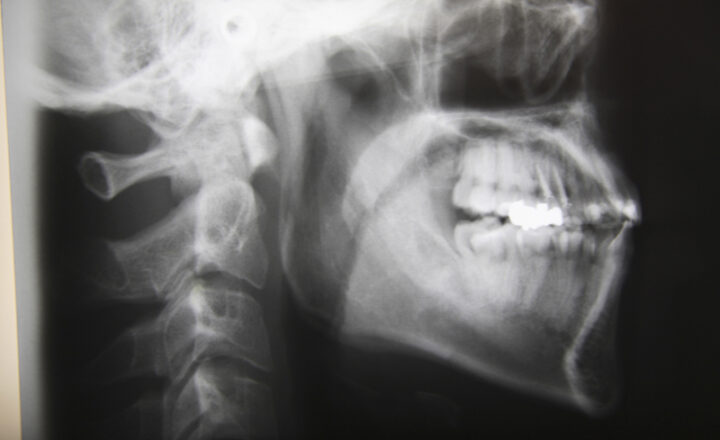



この記事へのコメントはありません。